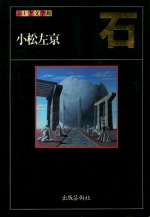 昨日讀んだ「余は如何にして服部ヒロシとなりしか」が角川ホラー小説大賞短篇賞受賞作とはいえ、その実ホラーというよりは奇妙な味の小説で恐怖という點では些か物足りなかったということもあって、今日は純粋に怖い小説を讀んでみようと思った譯です。
昨日讀んだ「余は如何にして服部ヒロシとなりしか」が角川ホラー小説大賞短篇賞受賞作とはいえ、その実ホラーというよりは奇妙な味の小説で恐怖という點では些か物足りなかったということもあって、今日は純粋に怖い小説を讀んでみようと思った譯です。
和モノに限らずやはり恐怖小説といえば短篇。となれば短編集の中からひとつと考えたのですが、筒井康隆編の「異形の白昼」はずっと昔にレビュー濟みだし、そうなれば困った時の「ふしぎ文学館」シリーズ、という譯で、小松左京の作品集「石」を取り上げてみたいと思います。
作者の恐怖小説の代表作といえば「くだんのはは」、ですよねえ。上に挙げた「異形の白昼」にもしっかり収録されていたこの名品、勿論本作にも入っています。
構成は大きく第一部と第二部に分かれておりまして、じわじわとやってくる怖さは第一部の方が際だっています。例えば「夜が明けたら」は真夜中の突然の停電に途方に暮れる家族を襲うところから始まるのですが、何やらスピルバーグの「宇宙戦争」フウの出だしと、遠くで車が走っている音がしているところなどから、これはもしかしたら宇宙人の侵略ものかと思いきや、バカSF系のトンデモないことが起こっていたというお話。暗闇の中の息苦しさと眞相が明らかになった刹那の絶望感がイヤーな感じの佳作でしょう。
「空飛ぶ窓」は雪景色の中へ忽然と現れた窓のお話で、このマグリットを髣髴とさせるシュールな景色は正体が知れないだけにぞっとするような怖さがあります。
「海の森」も村の中に響き渡る轟音の正体が知れない中盤までの展開が怖い。「空飛ぶ窓」では最後の最後にこの窓の正体が明かされるのですが、この作品では中盤を過ぎてからこ怪異の正体が徐々に明かされていきます。物語はこの眞相が判明していくにつれて恐怖の度合いが失速してしまうところが殘念なのですが、まあこれは仕方がないでしょう。ただ暗い海の底で姿なき怪物が群れている図は想像するだけで息苦しくなります。
「ツウ・ペア」は、掌についた血と女の髪の毛の正体がまったく分からないまま最後まで物語が進みます。これも幽霊なのか何なのかまったく事情が飮み込めない主人公の恐怖をそのまま味わうことが出來る物語の構成が見事。やはり「語らない」ことから滲み出る恐怖というのが、自分の求めている「怖さ」なんですよねえ。
「真夜中の視聴者」も、真夜中に突然テレビがついたり消えたりするというポルターガイスト現象をじわりじわりと描く筆捌きがいい。小松左京しかり、筒井康隆しかり、こういう昔の小説っていうのは、淡々と話を進めていくところがかえって怖いですよ。
「葎生の宿」は道に迷って民家を見つけた男がトンデモないことに卷き込まれるお話。迷い込んだ舊い民家には女の氣配があるのですが姿が見えない。薄氣味惡くなって男はその家を飛び出すのですが、追いかけてくるんですよ、「或るもの」が。考えると完全に莫迦莫迦しいんですけど、この追いかけてくる或るものがテンヤワンヤの騒動へと至る経緯が面白い。怖いというよりは、妙な笑いを誘う一編です。
「秘密」は曰くありげな人形が引き起こす呪いの話。妹がその呪いの人形に唾をかけたばかりに、封印されていた呪いが発動し、兄は義姉を殺して食べてしまう、という不條理な物語が展開します。それをまた淡々とした筆致で描いているものだから何とも坐りが惡く、その違和感がぞくりとくる怖さを釀し出しています。
續く第二部は表題作ともなっている「石」で幕を開ける譯ですが、これは或る「石」を手にした子供が天才となってしまう話。天才でいながら母親にベッタリと依存している子供と、その子供を溺愛している母親の樣子が不氣味過ぎます。人間らしさを喪失した子供に母親は強姦され、天才へと覚醒した子供を嫌っていた父親はその子供に殺されて、……という鬱な展開の結末は悲慘の一言。ぞっとするような怖さという點では収録作中一番でしょうかねえ。
「黄色い泉」は舞台の比叡からヒバゴンの話かと思いきや、予想外の方向に話が進んでいきます。道に迷った恋人の二人。腹をこわしたといって車を降りた女が姿を消し、男は彼女を捜すのですが、そこで彼は猿のような怪物に出會います。恋人は怪物に攫われたと確信して男はその後を追うのですが、……單なるヒバゴン噺かと思いきや、そんな仕掛けがありましたか、という結末に驚いてしまいましたよ。
そして名作「くだんのはは」へと續くのですがこの作品はもう説明無用でしょう。日本が敗戦へと突き進んでいく暗い時代背景を舞台に、僕の一人稱で語られる物語です。これは僕の一人語りで語られるからこそ、最後のオチが見事に決まっている譯で、當に語りの力を見せつける一編でしょう。お屋敷のうら暗い雰囲気といい、謎めいた部屋の中から運ばれる洗面器の中身といい、とにかくディテールから語りの進め方まで、當に「物語る」ことから生じる恐怖を堪能出來る名作でしょう。
「保護鳥」は名前に仕掛けられたネタが最後の一行で明らかになるところの冴えがいい。絶滅寸前の鳥を保護しようとしている外國の村が舞台なのですが、村の連中は頑なにその鳥がどんなものであるかを教えててくれません。興味を持った男は知らぬ間に村人たちに追いつめられていくのですが、最後になって明らかにされる鳥の正体とは、……というところで物語が唐突に終わってしまうラストも光っています。
「凶暴な口」はただひたすらエグい話で、平山センセも眞っ青なグロ描写が延々と續ます。手術臺にあがって廻転鋸で自分の脚を切断する冒頭から思わずウェッとなってしまう強烈な掌編なのですが、正直このグロ描写を書きたいが為にこんなフウに物語をデッチあげたんじゃないかと思うくらいです。オチも意味不明でとにかくキツいの一言。
「比丘尼の死」は本作収録の作品のなかでは恐怖というよりは現代の悲哀が餘韻を殘す一編。過去の比丘尼の物語から、唐突に現代へと飛ぶ後半、比丘尼の存在意義が明らかにされた瞬間に、デカタンな幕引きで終わるラストが秀逸。
「ハイネックの女」は樣々な騙しを凝らした作品で、離婚してしまった中年男が主人公なのですが、隣の住人は若い美人とよろしくやっていて、艶っぽい嬌聲が壁を通して聞こえてくるのに悶々とし乍らも、或る夜、奇妙なことに氣がつきます。隣のベランダから真夜中に飛び立つ鳥、そして大蛇の正体とは何なのか。自分は中盤まで女の正体は「蛇おばさん」かと思っていたんですけど、こんなものだったとは。
そして本作の最後をしめるのが「牛の首」というのも洒落ています。皆があまりに恐ろしく口にすることも出來ない「牛の首」とはいかなる怪談なのか。興味を持った主人公は「牛の首」の内容を突き止めようとするのだが、……という話。
あらためて讀み返してみても、やはり六十年、七十年代の小説っていうのはいいなあ、と感じてしまいました。何というか、語らないこと、というか引き算の美學とでもいいますか、とにかくその語らないところから生じる恐怖というのが際だっていて、それがまた自分好みなんですよねえ。飜って現代の小説というのはあまりに讀者に優しすぎて作者が語りすぎるきらいがあり、じわじわと本を讀んでいる後ろから怖いものがやってくるような恐怖感が希薄な感じがするのですが如何。
勿論現代の小説には現代の小説でしか味わうことの出來ない良さというのもある譯ですけど、やはり偶にはこういう舊い小説に立ち歸って、物語ることの力というのをじっくりと堪能してみたくなるのでありました。
