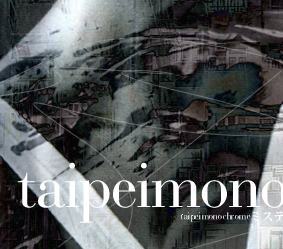「本格ミステリ館焼失」の作者、早見江堂氏の別名義による作品で、第五回鮎川哲也賞最終候補作の本作、「焼失」の後に讀みかえしてみると、なるほど、何となく「虚無」リスペクトの空気が微妙に感じられます。
「本格ミステリ館焼失」の作者、早見江堂氏の別名義による作品で、第五回鮎川哲也賞最終候補作の本作、「焼失」の後に讀みかえしてみると、なるほど、何となく「虚無」リスペクトの空気が微妙に感じられます。
内容の方は、靈能者と勘違いされている作家のオバサンが語り手となって、失踪したボーイの行方を搜すのだけども、某宅にて便器に頭をツッ込んで死んでいるゲロ死體を發見、そこにはワープロで記された譯あり手記もあって……、という話。
失踪したボーイ搜しという趣向からちょっとハードボイルドの風格の強い内容を予想してしまうものの、主役となる語り手は作家のオバサンで、自分の息子と二人暮らし。おまけにその息子の父親、つまりエッチした相手の名前をどうしても思い出せないという不可解な設定です。語り手の息子に対する気色悪い思いがさりげなく語られているあたりも見所のひとつで、上に述べた父親の名前を思い出せなかったりするところや、さらには息子が自分の母親のことをおばさんを呼んでいたりするあたりから、サイコっぽいお話かなア、なんて妄想してしまう読者はもうその時点で負け組の仲間入り。
失踪したボーイを搜していくとやがてド田舍の家へとたどり着き、そこで便器に頭をつっこんでご臨終という死體を發見、――と便器便器、とくどいくらいにこのあたりをディテールを語ってしまうのには勿論理由があって、このさりげなく記述されている違和感から、やがてボーイ搜しが自分探しへと転じていくという結構は、一編の小説としても見事にまとまっていると思います。
明快なかたちで提示されている謎は、便器に頭を突っ込んで死んでいた死體は誰なのか、というあたりで、そこに件の手記の書き手と記述の眞偽を巡って、中盤から物語はキモチワルイ關係にある母子の推理を中心に展開されていくのですけど、ミステリとしてこのあたりがチと弱いところがちょっとアレ。
というのも、失踪したボーイを搜していくという小説の起點には、語り手たちが關わることになるとあるきっかけがあって、それが最後にボーイの家族と語り手の家族とを照應していく構成が後半の大きな見所であり、かつ謎解きに託した大きな仕掛けのひとつではあるのですけど、この起點においてそのあたりの伏線も拔きにしてマッタク何も語っていないところから、この真相開示のカタルシスが激減しているところが勿體ない、という気がします。
ただ初読時は、本格ミステリとして、というよりはハードボイルド的な結構を期待して読んでいたがゆえに、このあたりの構成のぎこちなさもそれほど氣にならず感心した記憶があるので、案外、鮎川哲也賞を意識せずに手に取った方が愉しめるのかもしれません。
ひとつ、「虚無」絡みで非常に評価出来る点は、このアンチ・ミステリ的なハッピーエンドでありまして、信用のおけない語り手の手記から樣々な推理を導き出し、それによって事件そのものを虚無化させてしまうという結構は秀逸です。個人的には、このようなアンチ・ミステリ的な企みは、「焼失」よりも本作の方が成功していると思うのですが如何でしょう。
で、巻末の解説に鷹城氏曰く、彼女の「実質的なデビュー作と呼べる作品とはやはり、一九九一年刊の『かぐや姫連続殺人事件』ということになるだろう」とあります。この作品はどうやらバリバリのコード型本格らしく、鷹城氏は、
しかしながら、かぐや姫の見立てに、からくり屋敷、暗号、実行犯を操る真犯人といった本格ミステリ的ガジェットを多用した展開は、この作家の本領からは遠いところにあったように感じられてならない。今日の矢口敦子の出発点は、第二作にあたる本書『家族の行方』にあったと位置づけるのが適切であろうと考える。
と述べています。だとすると、「焼失」は、処女作の風格へ回歸した作品ということになりそうなんですけど、作者の矢口氏にはこの鷹城氏の言葉も屆かなかったということでしょうか。
解説には本作の特色のひとつとして、「少女漫画的な美形キャラをしばしば作中に登場させる」ところなどが挙げられているのですけど、「焼失」を讀んでいる間もそのあたりは十分に感じられたゆえ、おそらくはこういったところは完全に作者である矢口氏の趣味嗜好であろうかと推察されます。
本作では美形キャラを女が描くとなれば当然アレだよね、というゲスな読者の勘ぐり通りに作中人物がアレしていくという秘密が明かされていくのですけど、ここで上に述べたような仕掛けの甘さが感じられるところがアレなゆえ多くを語ることは出来ないところがちょっとアレ。
本作もまた自分のようなキワモノマニアよりは、御手洗と石岡君がアレしちゃうとか、榎木津と京極堂が生まれたマンマの姿で(オエッ)、――みたいな漫画や小説をものしてグフグフと含み笑いをもらしてしまうような腐女子には強力にアピールできる逸品といえるのではないでしょうか。
果たして早見江堂名義の「焼失」はあくまで手遊びに過ぎないのか、それとも原点回帰とばかりにあちらの作風を炸裂させていくのか、……腐女子の方々の生暖かい視線によるウォッチを期待したいと思います。
 傑作。ジャケからして恐らくはライトノベル的な讀みを期待されているかと推察されるものの、個人的には本格ミステリの技巧が炸裂した、非常に濃厚な一冊として大いに堪能しました。
傑作。ジャケからして恐らくはライトノベル的な讀みを期待されているかと推察されるものの、個人的には本格ミステリの技巧が炸裂した、非常に濃厚な一冊として大いに堪能しました。