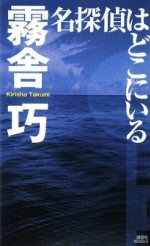 作者である霧舎氏曰く、「いまいちばん好きな作品」というのも大納得の逸品で、堪能しました。
作者である霧舎氏曰く、「いまいちばん好きな作品」というのも大納得の逸品で、堪能しました。
これまたあとがきに「何気ない台詞が、いちいち琴線に触れてくる」とある通りに、本作では呪いの短劍が喉に突き刺さって悪魔の仕業だ何だのと皆が皆をしてテンヤワンヤ……といった、一件ド派手に見えるけれども実は定式凡庸といった趣向は皆無。「何気ない台詞」も含めた登場人物たちのちょっとした言動や振る舞いの背後に隠された「思い」や「企図」が誤導や謎を構成し、それらが反転の構図と悲哀溢れる真相を描き出すという、まさに現代本格としての美しい結構を持った物語です。
とはいえ、ノッケから学生時代の主人公と娘っ子のムズムズするような胸キュンのラブ・シーンが大展開されるという見せ方はやはり霧舎氏で、「男の人に胸を触られたのだって、さっきの今寺くんが初めてなんだから……」「今寺くんのエッチ」「女の子にこんなこと言わせておいて、今寺くんからは何もなし?」「そっか、今寺くん、あたしと一緒に帰りたかったんだ」「うれしいよ、今寺くん」「うまいな、今寺くん」「そうじゃなくて……ずっとこのままでいたいなって、あたし思ったの」「さよなら、したくないな、あたし」――って引用しているだけでも背中がムズムズしてくるんですけど(爆)、しかしこうしたムズムズするようなシーンに鏤められた「何気ない台詞」、――とはいえ、読んでいるこちらはムズムズしっぱなしなので、決して「何気ない」ともいえないのですが、そうした言葉の背後に隠された企図が最後の最後にあるブツによって明かされるシーンは最高に感動的。
本作では脅迫事件や過去の双子が犯した、事故に見せかけた殺人事件など、ミステリらしい事件を凝らしてあるとはいえ、上に述べたようなある人物の強い思いを「謎――推理」の結構にのせて描き出しているのに比較すると、そうした事件の背景に対してはいかにも生臭い政治屋のリアリズムを添えてあるという対照性が面白いと感じました。
もっとも双子がしでかしたという「殺人」に關しては、冒頭から大胆な誤導が凝らされてい、これをまた霧舎氏がいうところの「何気ない台詞」に込められたミステリ的な技巧として見るのも一興でしょう。
ある人物のある行動がまた他の人物の思い違いを生んでしまうという偶發的な連鎖をも利用して人心を掌握しようとするある者の目論見と、「探偵」未滿である主人公の妻に対する思いを交錯させた描き方も見事で、各人の思うところが一息に明かされるのではなく、ひとつ、またひとつとフックとして物語に凝らしてみせたことで、ド派手な謎こそないものの、見えていた構図が次々とその色を変えていくという結構に昇華させていて、まったく飽きさせません。
そうしたとあるきっけかから事件に関わることになった「探偵」未滿の主人公がついに真相に知るにいたって、この二日間を振り返る幕引きのシーンも感動的だし、それのほんの少し前にも、そのブツが彼の元に届けられる前のいきさつを彼じしんは「偶然」と語り、それとは対照的に彼を愛し、信じる妻が「遺志」――というふうに、ここに何者かの「思い」が込められていると語るところも素晴らしい。
霧舎氏は最初の方に出てくる「いまはそんな方法しか思いつかない」という台詞がお気に入りのようですけど、そのほかにもこうしたグッとくる台詞は色々あって、ある推理を妻に対して語って見せる主人公がその推理について「夢も希望もない、論理的な考えだよ」というところとか、ある人物が過去を振り返りながら、主人公に対して「あの日から、あたし、誓ったの。絶対に……」とかいってそれを彼が「きれいになりましたよ」と返してみせるところとか、……というフウにちょっと頁を返しただけでも容易に二つ三つ拾い出すことができます。
登場人物の一言一言が、ある時はミステリの誤導として作用し、またあるときは絶妙な伏線として、さらには読者の心を揺さぶる感動点へと變じたりと、とにかくじっくり読めばそれだけ最後に明かされるブツの感動の奔流に涙腺は緩みっぱなしという、最近の小説には絶対に欠かせない「泣き」の要素も最大級にブチ込んである逸品ゆえ、「あかずの扉」シリーズの外伝とかそのあたりは気にせずとも、「泣ける本格」が読みたーいという年増スイーツの「女子」も安心して手に取ることができる一冊だと思います、……というか、スイーツだったら冒頭に描かれる学生時代の胸キュンなシーンもいっぱいに愉しむことができるのではないでしょうか。オススメでしょう。
 ドキドキ胸キュン、アリバイトリック。
ドキドキ胸キュン、アリバイトリック。