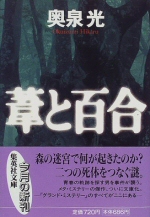 奧泉光をミステリ作家として見た場合、やはり「グランド・ミステリ」を推すべきなんでしょうけど、濃いのはこっち。「ノヴァーリスの引用」は中編ほどの厚さでしたけど、こちらはボリュームもあって作者は好き放題にやっています。
奧泉光をミステリ作家として見た場合、やはり「グランド・ミステリ」を推すべきなんでしょうけど、濃いのはこっち。「ノヴァーリスの引用」は中編ほどの厚さでしたけど、こちらはボリュームもあって作者は好き放題にやっています。
何しろ「虚無への供物」のいくつかのセンテンスはそらんじることができるというくらいの「虚無」好きの作者が書く物語ですから当然一筋繩でいくような話ではなく、横溝正史か或いは小栗虫太郎の「白蟻」を髣髴とさせる冒頭の難しい文章に始まり、奈々村久生のような女探偵が出てきたりする中盤の謎めいた展開といい、ミステリ好きにとっては御約束の展開が嬉しいところ。
しかしそれも後半に至って毒茸がもたらす幻覺作用も交えて物語は混沌としてきます。かつてコミューンがあった森の中、そして曰くありげな村、呪われた家系といったミステリ的要素を存分に詰め込みながらも、着地點は完全に幻想小説。
實際にあの事件はあったのかなかったのか、總ては妄想だったのか、どうとでもとれるような割りきりの惡いラストには當事色々な意見があって、どちらかというと否定的な見方が大半を占めていたように思うのですけども、今こうしてあらためて讀んでみると、やはりラストはこっちの方が良いですよ。
所々挿入される教授たちと学生たちの和氣藹々としたとぼけた雰圍氣は愉しく、このあたりは「ノヴァーリスの引用」と同じですねえ。アンチ・ミステリ好きだったら、手に取ってみる價値はある傑作。しかし好き嫌いを選ぶ作風であることは疑いなく、普通のミステリ好きが讀んだら噴飯モノの問題作ともいえるでしょう。
 ミステリ仕立ての小説というくくりがなくても愉しめる短篇がこの文庫に収録されている「滝」。芥川賞の候補にもなったそうですけども、堅い文章がちょっと慣れるまで讀みにくいのがちょっとアレなんですけど、リズムに乗れれば結構いけてしまうのが奧泉光の小説です。硬質な文章、そして少ない會話文という構成。また勲という名前からちょっと三島のあの小説を想起してしまうのは自分だけですかねえ。
ミステリ仕立ての小説というくくりがなくても愉しめる短篇がこの文庫に収録されている「滝」。芥川賞の候補にもなったそうですけども、堅い文章がちょっと慣れるまで讀みにくいのがちょっとアレなんですけど、リズムに乗れれば結構いけてしまうのが奧泉光の小説です。硬質な文章、そして少ない會話文という構成。また勲という名前からちょっと三島のあの小説を想起してしまうのは自分だけですかねえ。