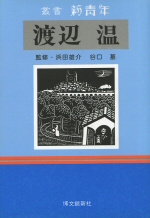 螺鈿の掌編集。
螺鈿の掌編集。
渡辺温といえば、あの渡辺啓助御大の実弟な譯ですが、兄の容赦ない悪魔主義の作風から同じ血族とは想像出來ないほどに繊細で美しい掌編が収められた本作は、作者の手になるシナリオや、映画隨想、さらには横溝正史も交えての座談會の内容までもが収録された豪華本。
短篇の中でまずミステリ好きとして挙げておきたいのは「嘘」でしょう。雪の降る晩、五六人が火のそばに寄り添って、それぞれが嘘つきの話をしようということになる。いよいよ井深君の順番になると、果たして彼の語るお話とは、……。
銀座の夕暮れを散歩していた井深君は一人の娘に出会います。彼女に声をかけられて二人でカフェに入ると、井深君は自分がしているネクタイピンにまつわる話を彼女にするのだが、……この後の、嘘を重ねに重ねてどんでん返しを決めていく展開が素晴らしい。さながら連城三紀彦のように一つの事実が嘘であったと覆され、それがまた、というかんじで最後にはその話そのものがひっくり返されるというメタ的なヒネリが絶妙な效果をあげている結末がいいですねえ。
以前鮎川哲也編の「怪奇探偵小説集(3)」に収録されていた「父を失う話」も、こうして作者の作品集の中に入ってみると、あの時に感じられた不氣味な雰圍氣よりも、幻想的な風格がより強く感じられます。
「少女」も「嘘」と同じく井深君の話なのですが、これまた彼が銀座の散歩中に無銭飲食をした少女を助けるものの、その時に思いついた井深君の嘘が妙な事態を引き起こして、……という話。ここでも物語の中の事実が輕やかな反転を見せます。物語の構成に探偵小説的なひねりを加えながらも、全體として見ると洒落た小咄やお伽話のように感じられるところが作者の風格でしょうか。
「兵隊の死」のナンセンスな作風も捨てがたいですねえ。こちらは春の日に兵隊が広い原っぱで青空に向けて銃を放つのだが、これが……というオチが何ともいえません。さらに古風な探偵が觀察と推理でもって、事件の眞相を見拔こうと試みるのですが、「兵隊の心に宿っていた最も近代的なる一つの要素」を検出出來なかった故に、それを果たせなかったという皮肉なラストがいい。何処かミステリ小説の結構に對して斜めに構えた作者の視線が微笑ましい一篇でしょう。
お伽話ふうの話が續く中で異彩を放っているのが「可愛そうな姉」で、唖の姉と二人で暮らす私を語り手とするこの物語は、私が大人になるのを拒む姉と私の二人に近親相姦を思わせる關係をほのめかしつつ、私が女性を愛することさえ許さない姉を最後には奈落の底に突き落とす結末が凄まじい。兄啓助御大のごとき悪魔主義がムンムンに感じられるこれまた傑作でありましょう。悪魔といいつつ、何処か現實感を伴わない、ふわふわとした雰圍氣が感じられるのはやはりその簡潔にして繊細な文体の故でしょうかねえ。
この「可愛そうな姉」と同樣の、やるせない結末が冴えているのがシナリオの「老いたる父と母」。引きこもりの息子と老夫婦となった父母のお話で、ある日サーカスに魅せられた父と母は息子に書き置きを殘して家を出て行ってしまいます。サーカス團に入り、「幸福な思いで泪ぐ」む老夫婦と、見捨てられた息子の最期を対比させたラストが冴えています。
まあ、こんなかんじで、一作一作それぞれが味わい深いのですが、本書は「叢書 新青年」シリーズの一册ということで、新青年で企畫された座談會も収録されているんですけど、その面子が作者である渡辺温に横溝正史という豪華な組合せ。この二人が毎回新進俳優や若手女優をゲストに招いてお話をするというもの。新青年というと硬派な探偵小説雜誌というイメージしか昔はなかったんですが、當事はこんな洒落た企畫もあったんですね。
これ、今でいうと、さながら有栖川有栖と北村薫が長澤まさみをゲストに招いて、とか、二階堂黎人と喜国雅彦が綾瀬はるかを迎えて今話題のドラマ「白夜行」を語る、なんてかんじですよねえ。
二階堂「綾瀬さんはミステリとかは讀まれるんですか」
綾瀬「ええ。東野圭吾先生の作品は前から大好きでした」
二階堂「じゃあ、最新作の『容疑者Xの献身』は勿論……」
綾瀬「直木賞も獲ったんですよね!あれも本當に面白かったです」
二階堂「でもね、僕はあの作品は本格ミステリとは認めていないんですよ。そもそも……」
喜国「二階堂さん、その話題はこういう場ではちょっと……」
今だとこんな會話が展開されるに違いありませんよ。
本作が素晴らしいのは、作品は勿論のこと、作者への敬意と作品に対する暖かいまなざしを感じることが出來るその本作りにありまして、ここまで編者の眞摯な姿勢が感じられる本というのも珍しい。装丁こそ地味なものの、「花束にかえて」というタイトルの解説も含めて、まさに中身で勝負というところが好印象。
この本、いつ買ったか記憶にないんですけど、奧付を見ると92年の初版ですから、もう十年以上も前の編集本ということになりますか。飜って最近の本というと、斬新な装丁に贅を凝らした、どうにもデザイナーの個性ばかりが際だったものばかりが目についてしまい、何だかなあ、と感じてしまうのでありました。
まあ、それでも本作のように、編集の眞摯な姿勢と意識が明快に感じられる本というのも勿論あって、例えば最近自分が讀んだ本だと、本の雑誌社からリリースされた「都筑道夫少年小説コレクション」とか、出版芸術社の「三橋一夫ふしぎ小説集成」とか、或いはちょっと古くなると日本評論社からリリースされた「天城一の密室犯罪教程」あたりでしょうか(すべてに日下氏が絡んでいるのが何とも)。
で、この「叢書 新青年」シリーズ、自分が持っているのは本作だけなんですけど、他のシリーズはどうなんでしょう。今回久しぶりに讀み返してみてちょっと興味が出て来ました。
他は久夫十蘭「遁走するファントマ」、聞書抄「まだ見ぬ物語のために」、小酒井不木「『幻想有理』の探偵劇」、谷譲次「言語表現の遠心力」。タイトルが素晴らしいんですけど、竝んだ面子はすでに他の本で手に入りそうなものばかりのような氣がします。かといってこのシリーズ、本屋で竝んでいるのは見たことがないし、かといって出版社である博文館新社のサイトを見ても、収録されている作品の情報はないしというかんじでありまして。せめて収録されている作品がどんなものなのかだけでも分かればいいんですけどねえ。
 帯に曰わく、「異形の妖獣が誘う変拍子の迷宮」。
帯に曰わく、「異形の妖獣が誘う変拍子の迷宮」。