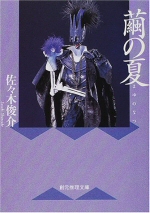 何ともいえない餘韻が殘る小説。二人の姉弟探偵が辿り着いた眞相というのは決して良いものではなかったのだけども、それでもこの夏休みの探偵ごっこを経たことによって変わってしまった二人が、ふと自分がたちが辿ってきた過去を振り返ったときを思うと、何というか、言葉ではうまく説明できない気持になります。
何ともいえない餘韻が殘る小説。二人の姉弟探偵が辿り着いた眞相というのは決して良いものではなかったのだけども、それでもこの夏休みの探偵ごっこを経たことによって変わってしまった二人が、ふと自分がたちが辿ってきた過去を振り返ったときを思うと、何というか、言葉ではうまく説明できない気持になります。
最近讀んだ氏の最新作、「模像殺人事件」と同樣、物語は淡々と進んでいきます。ただ、「模像殺人事件」と大きく違うのは、主人公となる姉弟がいきいきとしていること。この二人のキャラって、創元推理「日常の謎」派に特有のものだと思うのだけども、典雅な文章とも相まって、自分は日影丈吉を思い出しました。とにかくこの作者は文章はうまい。というか、本當にこの佐々木氏って、昭和四十二年生まれなんですか?文章だけ読んだらどうしたってそんなふうには思えないんですけど……。
トリックと呼べるのかどうか、一応犯行にはそれらしい「技」が使われますが、この小説の本旨はその犯行方法を暴くことにあるのではなく、「あの事件は何だったのか」、そして「その背後には何があったのか」という點にあります。このあたりは「模像殺人事件」とも同じといえば同じですけど、うーん、……自分はこの眞相を見破ることは出來ませんでした。確かにチャンと書いてありますよね。それも非常にさりげなく。このさりげなく描かれた事実を組み合わせていけば確かにそういうふうに推理することは可能だった、とは思うのですけども、完全に作者にやられてしまいました。
何かこの物語は、ときおり思い出しては、また讀み返したくなってしまう、……そんな本になりそうです。大傑作と手放しで推薦できるミステリではないのですけども、小説としては極上で、「模像殺人事件」よりも大くの讀者に訴える力を持った物語だと思います。
