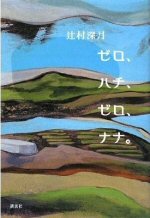 とある人から「ゼッテー面白いから読んでみて」と勧められた一冊で、自分から積極的に手に取ってみたわけではないとはいえ、個人的には非常に堪能しました。ただ、読了したあと果たしてこの感想をブログに上げるべきか少し悩んだ作品でもあったりするのですが、このあたりについては後述します。
とある人から「ゼッテー面白いから読んでみて」と勧められた一冊で、自分から積極的に手に取ってみたわけではないとはいえ、個人的には非常に堪能しました。ただ、読了したあと果たしてこの感想をブログに上げるべきか少し悩んだ作品でもあったりするのですが、このあたりについては後述します。
物語は、母親を殺して失踪した、かつての友人の行方を追いかけるライターの物語を第一章に、そして第二章では、事件の真相と暗合めいたタイトルに隠された意味を、コロ助娘との暖かな交流も交えて描き出す、――という結構です。
ライターと失踪した女の「友情」、そして二人の女の「母娘の関係」というものが大きな主題として取り上げられており、第一章では、「事件」を起こして失踪してしまった娘の関係者が、「探偵」の視点によって描かれていきます。「探偵」役を務めるライターによって、どちらかというと目立たない、ごくごくフツーのひとだと思っていた失踪女の印象が次第に変化していくという、――ミステリでは定番の展開を見せながらも、本作では失踪娘とその事件の被害者である母との本当の関係が明らかにされていくうち、探偵自身も自らの立ち位置と母との関係という現実に対峙しなければならなくなるという結構が秀逸です。
かといって、本作は「探偵」がこの事件にかかわる過程で大きな成長を見せるかというと、そんなことはなく、ここで昇華されるのは「探偵」の内面というよりは、失踪女との友情であるというところが興味深い。
……と、ここまで書いたところで、自分がこの物語をここで取り上げることを躊躇った理由についてツラツラと書いてみますと、本作ではダブル・ミーニングや誤導など、本格ミステリ的な技巧を鏤めてあるとはいえ、それらは決して大きく前面に押し出されることなく、むしろ可能な限りそうした技巧が使用されていることを最後まで読者に気取らせないような心配りがなされているように感じられます。
また上にも述べたようなライターを「探偵」とみなした讀み方をすることも可能とはいえ、この事件の眞相は「探偵」の「推理」によって繙かれるわけではありません。「友情」「母娘の関係」という明確な主題のなかでは決して見えていなかった意外な人物の「直感」によって最後の最後に事件の眞相が明らかにされるのですが、そうした趣向がまた本作をして「本格ミステリ」として読まれるのを拒んでいるのではないか、……と感じた次第でもありまして、果たして自分のようなボンクラがこんなふうに技巧だ何だといってこの物語を語っていいものか……ここまで書いても未だに悩んでいるところがアレながら、それでもこうして書き始めてしまった以上、とりあえず先を続けます。
まず「プロローグ」ともふられていない冒頭の「事件」を描いたシーンからして、中町ミステリ的な細やかな仕掛けが凝らされています。しかしながら、再読して始めて言葉の二重性やほのめかしに氣づかされるというここでの技巧は、読者を騙すというよりは、再読によって主人公の一人であるチカの内面に隠された本当の気持ちをくみ取ってもらいたい、という作者の企みのようにも見えてきます。
というのも、そもそもこの「大事件」と括弧書きにされているこの殺人「事件」についても、本格ミステリ的な真相開示という点からすれば、それほど大きな驚きをもたらすものではありません。しかし、たとえばこのモノローグでさらりと書き流されている「一年」という「猶予期間」の言葉の二重性など、第一章の最後まで「探偵」と読者を誤導させるために用いられた仕掛けは非常に纖細で、初讀のときにはそもそもここに意味が隠されていることさえ気がつかないほどに、本格ミステリ的な仕掛けとしての違和感を見事なまでに脱色させているところが素晴らしい。
本作が、本格ミステリ的な読みを行った場合に特異な結構だなと思わせるものは、上にも述べたような真相開示の方法のほかにも、第一章の最後に「探偵」がたどり着いた「真相」が第二章の最後ではあっさりとうち捨てられ、「探偵」の探偵的行為のみならず、「犯人」が事件後に行った様々な行為までを無化してしまうところでしょう。
本格ミステリ的などんでん返しの驚きを拒んだかのように見えるこうした後半の展開が、では意味のないものかというとそんなことはなく、この虚無的なあがきが最後には二人の本当の友情を生み出すという帰結が、本格ミステリ云々というよりは、小説として非常に巧みです。
「探偵」の探偵的行為が素直なかたちで真相を明らかにしないという本格ミステリ的には倒錯した結構を備えながらも、やはり「探偵」という本格ミステリ的な要素をピースとして當て嵌めてみないと物語に隠された真意が見えてこないという点では、近作では米澤氏の最新作である「追想五断章」にも通じるところがあるカモしれません。
平凡で幸せな家庭に思えたチエが事件の当事者となり、明らかに歪んだ母娘の関係を持ったライターのみずほが「探偵」を演じることになってしまったという倒錯は、結局、明らかにされた「真相」はチエの「事件」ではなく、自分の母が隱しとおしていたものだったという結末も苦い。
タイトルの意味についても一筋繩ではいかず、チエの母の、娘に対する思いを「真相」として知ってしまった読者がその真意を「どちら」に受け止めるかについても読者の判断に委ねられてい、本来であれば「探偵」の「推理」によって明らかにされる件の「大事件」の真相も、結局は物語の外――「母娘」という関係からは「見えないひと」となっていた人物の「直感」によって明らかにされるという非本格的な結末や、「本格ミステリ」として読むと見えてくる後景の構図が脱色された纖細な技巧によって隠されている結構など、非常によく練られた作品だと思います。
ただ、この作品の素晴らしさを伝えるにしても、自分のような本格読みがこんなふうにイチイチ語るのは寧ろ逆效果で、フツーの小説読みの「女子」が「感動しました!」と一言でその感想を述べた方が遥かに説得力があるような気もします。現代本格のマニアでも十二分に愉しめる逸品ながら、やはり本作はそうしたところにはこだわらず、素直な気持ちで読むべき一冊といえるのではないでしょうか。
