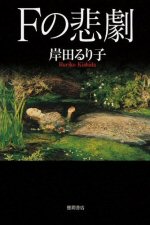 「出口のない部屋」などキワモノ風味を横溢させた風格から、「天使の眠り」「めぐり会い」という本格ミステリの技法を用いながらも感動のフレーバーを絶妙に効かせた路線へと進化を遂げてきた岸田女史の最新作。今回は、「天使の眠り」「めぐり会い」の徳間からのリリース。結論からいうと、「天使の眠り」「めぐり会い」の風格を踏襲しながらも「ランボー・クラブ」にも通じる不可能犯罪を織り交ぜた作風で、堪能しました。
「出口のない部屋」などキワモノ風味を横溢させた風格から、「天使の眠り」「めぐり会い」という本格ミステリの技法を用いながらも感動のフレーバーを絶妙に効かせた路線へと進化を遂げてきた岸田女史の最新作。今回は、「天使の眠り」「めぐり会い」の徳間からのリリース。結論からいうと、「天使の眠り」「めぐり会い」の風格を踏襲しながらも「ランボー・クラブ」にも通じる不可能犯罪を織り交ぜた作風で、堪能しました。
物語は、病的に抜群な記憶力を持つ娘っ子が不可思議な予知能力を働かせて、子供のころに描いた絵にあるものと同じペンションを発見、何でもそこでは自分の叔母にあたる人物が不可解な死を遂げており、彼女はそこに暮らしている住人から聞き込みも交えつつ、過去の事件の謎を解こうとするのだが、――という話。
殺された叔母は元女優で、何やら怪しい連中に追われてこのペンションにやってきたらしいことが早くも明かされ、物語は娘っ子のパートとこの元女優である叔母のシーンとを交錯させながら進みます。いわば定番ともいえるこうした結構からすると、二つのパートが最後に交わるところから真相が立ち現れる、……という展開をイヤが上にも期待してしまうわけですが、本作でやや意外なのは、この叔母が死ぬ前に産み落としていた赤ん坊の謎が後半で存外にアッサリと明かされてしまうところでありまして、ここから物語は件の出自の謎よりも、叔母の死という不可能犯罪の方へと焦点が当てられていきます。
当時の住人にはアリバイがあり、どう考えても叔母の殺害は不可能。では犯人は、叔母が話していたという怪しい組織の者なのか……とこの組織についてはやや陳腐化した設定がなされているものの、これが叔母と娘っ子の不可思議な能力に絡めて語られていくゆえ、それほどの違和感はありません。
本作には二つの謎が前半から同等の比重をもって語られていきます。ひとつは上にも述べたような叔母の不可解な死で、もうひとつが叔母の死とともに失踪した赤ん坊の行方ということになるわけですが、この二つの謎に添えられた細部としてあるブツの行方や、暗号めいたやりとり、さらにはある人物の体に残されていた痕跡などが鏤められ、それが二つの謎が解かれていくことで伏線へと転じていくあたりは非常にスマート。
ただ、やや評価が分かれるかな、と思わせるのが、不可能犯罪と出自の謎という二つのいずれかに読者が焦点を合わせて読んでいくか、というところでありまして、個人的には出自の謎についてはもう絶対にこれだろう、と勘ぐりながら讀み進めていった挙げ句、最後にマッタク予想を裏切らない、というか、やや腰砕けともいえるほどに後半でアッサリとこの真相が明かされてしまったゆえ、その時だけは口ポカーンとなってしまいました(苦笑)。
ただ、この予想通りの真相が明かされたあと、その前にこの人物が赤ん坊だろう、と確定していた人物のある痕跡が新たな謎となって立ち現れるという結構は秀逸です。ただ、これもまたやや駆け足で語られてしまうところはもったいないというか、何というか……このあたりに不満を感じつつ、最後の本丸ともいえる不可能犯罪については、猿でも判るトリックを用いてゲス野郎の犯行となってジ・エンドとなるあたりの容赦のなさは、「出口のない部屋」以降、ややおとなしくなっていた岸田女史のキワモノの個性の復活と受け止めるべきなのか、それとも……と頭を抱えてしまいました。
などとダラダラ書いていくと不満ばっかりじゃねーノ、なんて思われてしまうやもしれないので、慌てて付け加えますと、本作は出自に絡めた真相に仕掛けを求めず、また件の不可能犯罪についても、「本格ミステリ」的な、――「事件」に添えられたトリックに拘泥しなければ、実際、かなり愉しめます。
というのも、叔母のパートで彼女を助けるある人物との隠された交流が、もう一つの事件の真相開示によって非常に幻想的なシーンとして描かれ、また現在の場面でも、出自の真相が明かされたあと、前半でチラっと脇役で登場したある人物にスポットライトがあてられ、それが最後の最後、これまた舞台の京都にふさわしい幻想的な情景として活写されるところなど、幻想ミステリを暗示させるような予知能力といったフレーバーが、現実的な解を得たあとに大きな意味を持ってくるあたりに、ガチな本格ミステリというよりは、より普通小説に近い、それも抒情と人間描写を効かせたミステリーとして受け止める物語であることを主張しているようにも感じられます。
実際、二つのパートが本格ミステリ的な連関を見せず、現在の謎解きのパートでもややあっさりとしたかたちで二つの謎の真相を明かしてみせる一方、叔母の場面では影の役割を果たしていた人物の死の真相を明かす場面で美しい幻想を現出させ、また現在のパートでも幕引きには幻視を際立たせてみせるなど、リアリズムに比重を置いた本格ミステリというよりは、より幻想へと傾斜した普通小説として読んだ方が本作の妙味を堪能できるのではないでしょうか。
それもこの物語がかなりの強度を持っているからでもあり、実際、本格ミステリマニア的視点でこの物語を精査すれば、例えば出自の謎についてなど、この作品のように構築して、出自の謎が解かれた瞬間に叔母の生き様を感動的に描き出すこともだって充分に出來た筈だし、不可能犯罪についても、件のペンションの怪しい住人を書き込んでみせることで、例えばこの作品のような異様な雰囲気の中に本格ミステリ的な技巧を凝らした逸品に仕上げることも出來たに違いなく、……それでも敢えて幕引きと件の人物の死の描写に幻想を活写したところに、現代の空気を敏感に感じ取った徳間の担当編集者の采配が感じられ、……と見るのは穿ちすぎでしょうか。
個人的にはキワモノ風味もやや効かせて騙しの結構に組み上げた「めぐり会い」の方が好みですが、その一方で読了したあと、本を閉じて物語を思い返すにつけ、大きな存在感を持って迫ってくる叔母の姿と、彼女を助けた人物の末期のシーンだけでも個人的には大満足。安心の徳間レーベルからの刊行ということで「天使の眠り」「めぐり会い」路線ともいえるし、不可能犯罪に注力したという点では「ランボー・クラブ」の風格も含んだ一作ということができる本作、「天使の眠り」「めぐり会い」がツボだった人であれば必ずや満足できる一冊、といえるのではないでしょうか。
 昨年、御大が訪中し、上海を訪れた際にファンへ配布された「外灘画報」に御大のインタビューが掲載されています。
昨年、御大が訪中し、上海を訪れた際にファンへ配布された「外灘画報」に御大のインタビューが掲載されています。