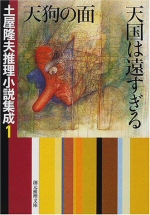 長野の寒村を舞台にした連続殺人事件を扱う著者のデビュー作。正史に比べると怪奇趣味もないし、どうにも野暮ったいなあ、なんて感じていた自分が莫迦でしたよ。今回、讀み返してみて、思いの他「凄み」を持った小説だということを思い知った次第で。
長野の寒村を舞台にした連続殺人事件を扱う著者のデビュー作。正史に比べると怪奇趣味もないし、どうにも野暮ったいなあ、なんて感じていた自分が莫迦でしたよ。今回、讀み返してみて、思いの他「凄み」を持った小説だということを思い知った次第で。
今回讀んだ創元推理文庫版には雄山閣版,浪早書房版のジャケが掲載されているのですが、浪早書房版のジャケ帯に曰わく「江戸川乱歩賞 第二位!」って、……乱歩賞に一位とか二位とか三位とかあるんですか。知りませんでしたよ。
まあ、そんな茶々はこれくらいにして本編に進みますと、序章「天皇の住む村」は、「会いに来たかよ 牛伏村へ ……ホンニヨイヨイ山そだち」なんていうヌル過ぎる牛伏音頭の引用から幕を開けます。
寒村、といっても正史のそれとは違って、微妙に近代化されているところが今から見ると野暮ったさを感じてしまう所以でしょうか。おどろおどろしい村の因習と戰後の澱んだ背景が釀し出す怪奇趣味だけで探偵小説の舞台を組み上げた正史とは異なり、本作では村の合併推進を巡る選挙なども背景にあったりするのですが、下手に近代的な要素を加えてしまったが為に、かえって時代の風化の影響を受けてしまったような氣がします。
事件は村の合併推進を畫策する村會議員選挙を迎える寒村で起こります。この村では女が天狗を崇める新興宗教をやっておりまして、村會議員のひとりがこの儀式の最中に毒殺されます。當然皆が見ている前で犯行が行われた譯ですが、犯人はどうやってこの衆人環視の中で毒を盛ったのか、というところが謎のひとつ。
さらに事件は續いて、同じ夜に二人の男が絞殺されます。これも怪しい人間にはアリバイがあって、誰が犯人なのか検討もつきません。果たして第一の事件と、第二第三の犯行は同一人物によるものなのか。村の巡査がその謎に挑むのですが、そこに巡査の知り合いの名探偵が村にやってきて、……というかんじで話は進みます。
本作で際だっているのは、冒頭からカッコ書きで作者が鬱陶しいくらいに物語に割り込んでくることでしょう。そもそも序章の終わりには「讀者よ」と語りかけて、「すべての事実が明らかにされたとき、この序章こそ、実は解決のための終章であったことを覚れるに違いない」というふうに、作者がいかにも大時代的な言い回しで氣取った台詞を吐いているのが古くさいというか何というか。
さらには巡査の人となりを少しばかり述べるときにもカッコ書きで茶々を入れたりしているし、第二の殺人で死亡推定時間が明らかになった時にもわざわざカッコ書きで解剖結果の一致と、二つの殺人がどのような順番で行われたのかをくだくだしく説明したり、アリバイのトリックを疑う讀者に向かってそんなことはないといったりと、讀み進めている間はこの作者の語りが相當に鬱陶しく感じられます。
しかしこの感想がまったく逆の方向へと轉じるのは犯人が明らかにされたあとでして、これだけ作者が讀者に向かって語りかける推理小説とあれば、當然ながら探偵が犯人を指摘する前に、例のもの、乃ち「讀者への挑戰状」が挿入されているのが當たり前、と考えるじゃないですか。
しかし本作は違うんですよ。本來であれば讀者への挑戰状が挿入される前に、犯人は死んでしまい、そのあとになって探偵は死んだ人物が犯人だったと唐突に語ります。そして、えっ、推理はどうなっちゃったんですか、という讀者の戸惑いをよそに物語は終章へと入ります。
ここに至って「讀者よ。……作者はここに、事件の真相を伝えると共に、……ささやかな袂別の宴を催したいと思う」というくだりとともに、有名な「事件÷推理=解決」の公式が提示される譯です。
そして作者は物語の冒頭から登場していた巡査の名前を挙げて「土田巡査自身、この物語の謎を解き得たかも知れない」と述べ、「一つぐらい、未解決で終わる探偵小説があってもいいではないか」と自らが掲げた探偵小説の公式を否定してしまおうと傾きます。
しかしすかさず「このような作者の意図にもかかわらず、事件の中途において白上矢太郎(本作の探偵)の登場を見たのは、結局、作者の敗北を意味する。探偵作家の悲哀であり、探偵小説の持つ「業」深さでもあろう。未解決の探偵小説などという、作者の夢破れ去る瞬間でもあった」と語り、本作は作者の意図に反した失敗作であったと宣言してしまいます(え、ええッ?)。
勿論この言葉には深い意味がある譯ですが、更には作者はここで「一つの復讐」を企図し、「名探偵を窮地に追いやり、作者の予想を裏切った登場に対して、あらん限りのイヤガラセを企て」ます。
探偵が或る人物を犯人だと断言した、ということで、作者はこの人物を、探偵が推理を述べる前に抹殺してしまうのです。そして「被害者も犯人も、すべてが消え去った後に、彼はいかなる解決を物語り得るか」と探偵に迫ります。そして作者は探偵があやふやな、確かめることの出來ない推論を探偵が述べ立てた時こそ、「讀者と共に、彼の推理の誤りと不確実なる点を、容赦なく追及してやればいい」と讀者に自らと共に探偵を責め立てやろうと持ちかけるのです。
探偵小説が持つ業に抗おうと、その探偵小説の必然的装置である探偵を窮地に追いやり、犯人を抹殺する、……ここで、本作における作者のくだくだしいまでの説明の企図が明らかにされるのでありました。それらは探偵小説が孕む業との格闘の結果、もたらされたものであったのだと。
作者が前に出て鬱陶しく物語を語る、という古くさい結構が採用された意図が明らかにされる後半には、探偵小説に挑んだ作者の凄みが感じられ、今の視點で讀むとかなり衝撃的でありました。辻真先あたりがやりそうな手法ですけど、それをこの古くさい小説形式で敢えて試みた作者のセンスに感心した次第です。
推理小説として見た場合、第二第三の殺人に關していえば、探偵が強調している或る點に着目すれば、眞相に辿り着くのもそう難しくないと思います。第一の殺人の仕掛けは流石に論理的に突き止めることは出來ませんでしたけど。
寧ろ本作の場合、ダサい舞台装置と古くさい小説形式を採用しながら、今日的な視點で見るとかなり斬新なことをやっているという點が評價されるべきではないでしょうかねえ。舊い作品も莫迦にしないで、折を見て再讀しないといけないなあ、と思い知らされたのでありました。
