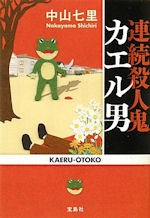 中山氏の小説は本作が初めてなのですが、屍体と犯人が描かれていながらもユーモラスでほっこりしたかんじのジャケとは対照的に、殺しのセンスはかなり陰惨。フックで吊したり、プレス機でペチャンコにしたり、生きたまま焼いたりとやりたい放題のシリアル・キラー、カエル男の正体はいかに、……という話。
中山氏の小説は本作が初めてなのですが、屍体と犯人が描かれていながらもユーモラスでほっこりしたかんじのジャケとは対照的に、殺しのセンスはかなり陰惨。フックで吊したり、プレス機でペチャンコにしたり、生きたまま焼いたりとやりたい放題のシリアル・キラー、カエル男の正体はいかに、……という話。
とはいえ、グロ屍体に幼稚な文章を綴ったメッセージを残して犯行を繰り返すカエル男が何者であるのか、被害者のミッシング・リンクを警察がたどっていくという本格ミステリらしい展開を見せつつも、後半のどんでん返しまでは、カエル男の暗躍によってパニックへと陥る市民と社会の様相の変化に焦点が置かれているのが、本作の個性でありまして、これがまた二転三転する真相の暁に明らかとなる真犯人の動機と密接に関わっているところが秀逸です。
探偵役となる刑事の視点から描かれる事件の展開にくわえて、犯人とおぼしきシリアル・キラーの過去が語られていくという結構で、この幼児虐待も交えたシーンもかなり辛く、正直ジックリと読み進めるのがかなりアレだったりするわけですが、この過去の逸話にも二転三転の二転目への仕掛けが巧妙に隠されているところなど、シリアルものには定番の虐待の過去というありきたりな情景を逆手にとって、読者を見事に欺いてしまう手腕は相当のもの。
何となく一番怪しい輩が捕まってしまうと、ああ、やっぱりそうきたか、と思っている暇もなく、それを影で操っていた真犯人が明らかにされ、事件はハリウッド映画モンめいたアクションを大展開、謎解きのみならず、そうしたサスペンスでもしっかりと見せ場を用意して読者を愉しませてみせる技法もまた巧みながら、これでも終わらず、まだまだ操りがあるよッとばかりの濃厚さは本格ミステリマニアならずともニヤニヤしてしまうところでしょう。
――とはいえ、本作が不思議なのは、読者を飽きさせようとしない作者のサービス精神ゆえなのか、思いのほかさらさらと読み進めてしまえるゆえ、そうした二転三転する真相についてもガチガチな本格のミステリのどんでん返しを体験しているときほどの高揚を感じることができなかったことでありまして、このことについて考えるに、その二転三転する真相がどんでん返しをするならやはりコレとコレだろうな、という想像の範囲内で、その犯人像に関しても既視感がありまくりなことが理由だったのカモ、と感じた次第です。
とはいえ、フーダニット的展開を期待させながら、後半ギリギリまで、操りをさらに操っていたラスボスの動機を際立たせるために社会派めいた問題提起を添えつつ、どんでん返しの最後で一気にそれを読者にブツけてみせた結構は巧みで、さらには第一の殺人にもしっかりと説得力をもたせたトリックで固めてみせたところも素晴らしい。
そして、事件は探偵の敗北によって終わったかにみせておいて、殺人輪舞とでもいうべきブラックな未来を予感させる最後の一行でキッチリとしめてみせたところなど、冒頭の一ページから最後の一行まで決して読者を飽きさせないという、作者の徹底した姿勢にはもう脱帽。本格ミステリ的仕掛けを凝らしながらも、あえてクドさを感じさせないどんでん返しの見せ方など、スマートな風格はグロ屍体への耐性が十分にあるならばかなり愉しめる一冊といえるのではないでしょうか。
